タイムカードや手書きの出勤簿、業務日報など従来の出退勤時刻の把握方法に代えて勤怠システムを導入する場合、労働時間がきちんと集計できるようになるまでにはいろいろな設定を適切に行う必要があります。
例えば所定労働時間を登録し、始業時刻より前に打刻があった場合にそれをどう処理するのか、残業時間としてカウントするのかしないのか、また、カウントするなら何分単位で集計するのか、といった具合に、様々な設定項目を会社の実情に合わせて設定していきます。

もちろん、新しいシステムを導入するわけですから、労働時間が適切に把握できるよう今までよりコンプライアンスを意識したものへと変更することになると思いますが・・・。
私どもがお勧めしている勤怠システムはタッチオンタイムといいますが、キングオブタイムと同じものです。
その設定は、お使いのスマホやパソコンを自分好みの設定に変更したりする作業と似ていますが、私どもの事務所がある程度のやり方を教えて、場合によってはお客さん自身がマニュアルを読んだり、サポートに電話して教えてもらいながら進めていくことになります。

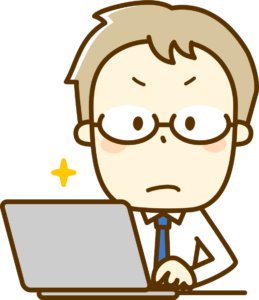
この設定作業、パソコンの設定が得意な人だと、めちゃくちゃ面白いと感じるのではないかと思います。私自身も楽しく感じているので、何かを組み立てたり、問題解決するのが好きな人には向いている気がします。



