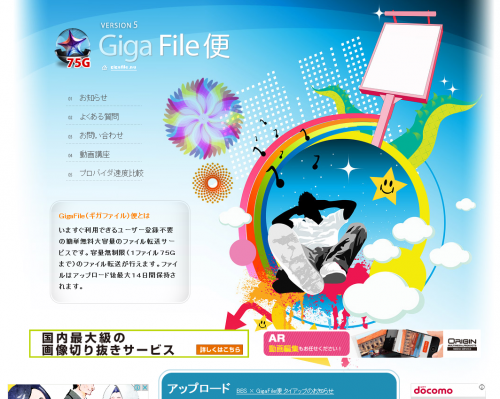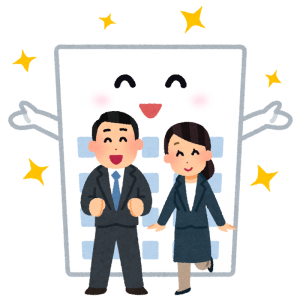添付ファイルのお約束
仕事上、パソコンやモバイル端末を使ってメールのやり取りをする中、ファイルを添付して送受信することが少なくないと思います。ファイルの種類としては、エクセルやワードで作成したものが業界に関わらず多いのではないかと思います。
業務に必要なファイルを簡単に相手に送ることができるため、メールに添付する方法はとても便利なのですが、ファイル容量には注意が必要です。
添付ファイルの容量に制限を設け、大きいサイズのファイルは送ることも受け取ることもできないルールになっている会社が多いからです。
具体的には3メガを超えたファイルの送受信制限を設けていることが多いようです。
そのようなルールを知らずに送ったメールが先方に届かず、エラーメールとなって戻ってきたことで慌てた経験をされた人もいるのではないでしょうか。
ファイル容量の注意点としては、こういったルールのない場合においても常識的なファイル容量といったものがあります。大容量のファイルを受け取ると、受信に非常に時間がかかったりメールソフトが反応しなくなったりするからです。
また、メールサーバーの容量が限度に達してしまい、その他の大切なメールを受け取れなくなる事態にもなります。
このように先方に迷惑をかけないためにも、最近では2メガ程度までに抑えることが適切だといわれています。
ファイルを転送してもらえるサービス
多くの画像を添付したファイルやページ数の多いファイルはどうしても大容量となってしまいます。メールに添付できない大容量のファイルを先方に送る方法としては、「ファイル転送サービス」がおススメです。
これは、転送サービスを提供している会社のサーバーにファイルを転送し、受け取る人はそこからファイルをダウンロードするという仕組みです。
ブラウザで開いたウェブサイトからファイルを転送するので、とても簡単で費用もかかりません。
この手のサービスはいくつかありますが、仕事上の大切なファイルを扱うことが多いので、安全性などに配慮されたサービスが望ましいですよね。
その中で利用者が多い2つのサービスを紹介します。

「宅ふぁいる便」
https://www.filesend.to/
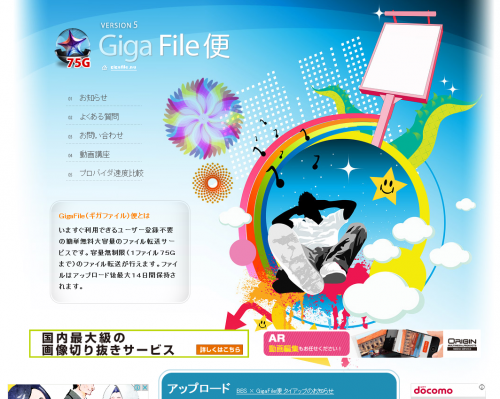
「GigaFile(ギガファイル)便」
http://gigafile.nu/
わたしは昔から「宅ふぁいる便」を利用しています。
メーリングリストの登録ができるので、アドレスの入力間違いもなく便利です。
また開封通知やダウンロード通知があるので、先方がダウンロードしたことが把握できて安心です。
大塚